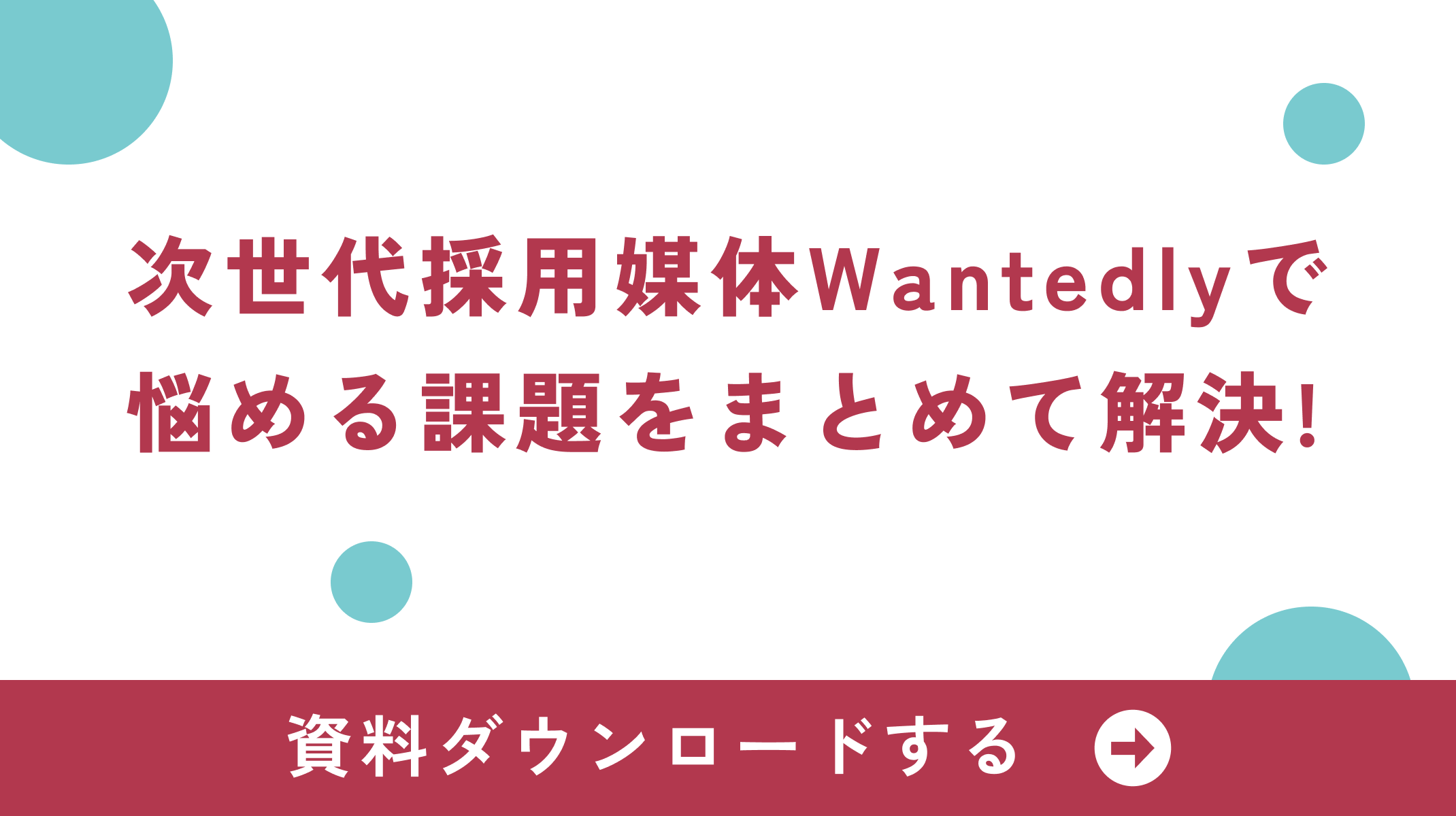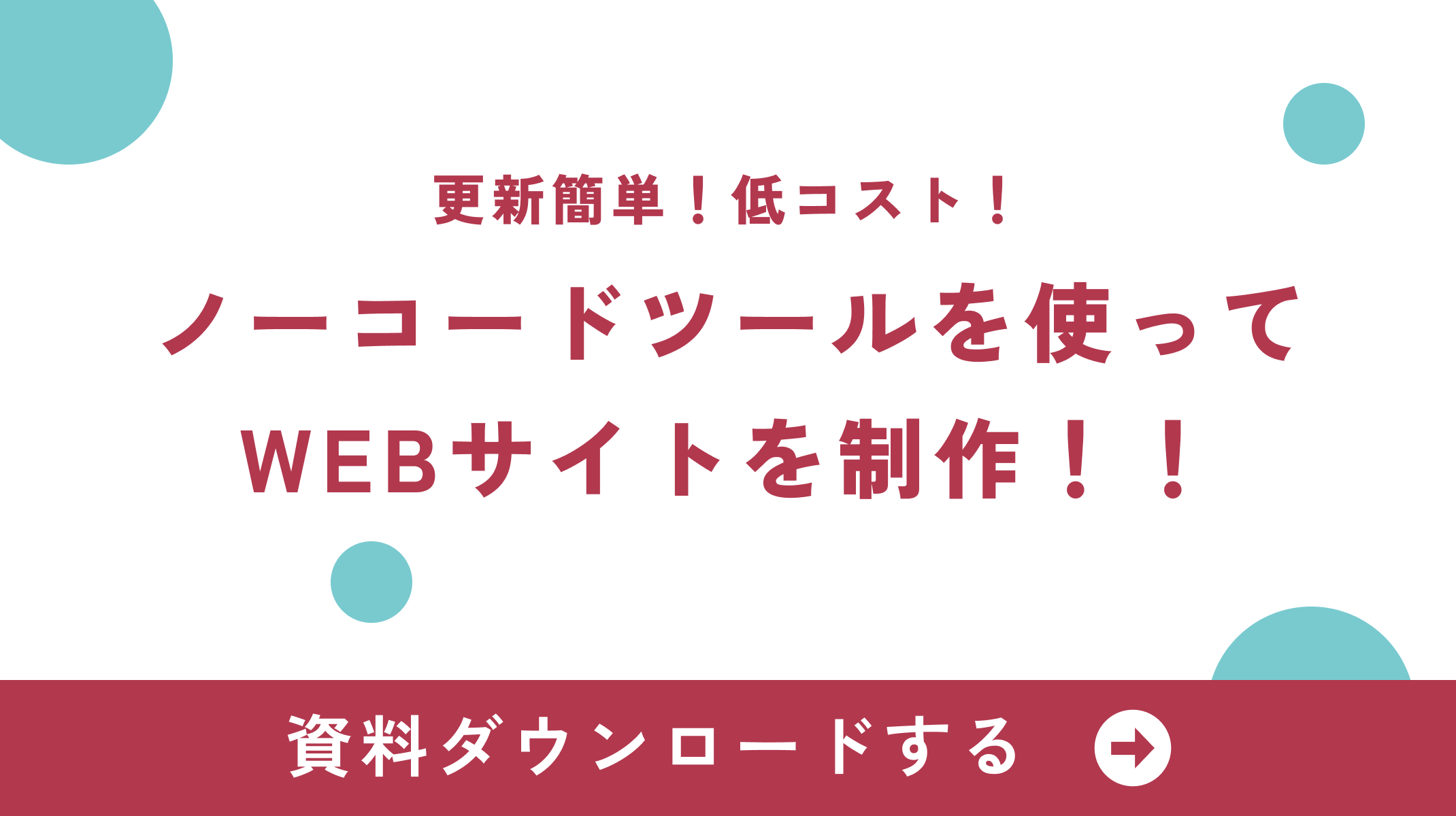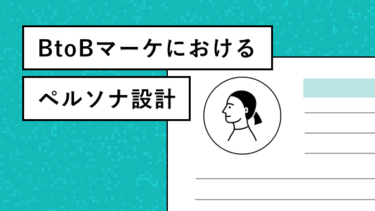私たちは、日々、様々な仕事をしています。
最初は、慣れておらずスムーズに進めることができなかった仕事であっても、経験を積み、知識を蓄えることで効率的に処理できるようになったりすることがあるでしょう。
こうして得た知識や経験、ノウハウを、後輩や若手に共有することで、より円滑に仕事を進められるという理屈は、多くの人が同意するところです。
しかしながら、理屈としてはそれを理解できていても、なかなか言語化して伝達することが難しい知識や経験というものがあるのもまた事実であるといえます。
こうしたものを「暗黙知」と呼びます。
この記事では、この「暗黙知」とはどのようなものか、そして、暗黙知をうまく組織内で共有し業務に活用していくにはどのような工夫が必要であるのかについて解説します。
「暗黙知」とは

暗黙知とは、一言で言えば「経験」「勘」「直感」などの「数値化・言語化」することが難しい知識のことを指します。
この「暗黙知」という言葉は、1966年にハンガリーの物理化学者・社会科学者のマイケル・ポラニーが提唱した「暗黙知の次元」という概念が元となっています。
暗黙知は、言語化が難しい知識であるというそれそのものの意味から、言語化して具体例を提示することもまた難しいものですが、日本の企業文化はこれに該当する知識が、数多くあるでしょう。
日本の企業文化の中でも、「マニュアル化されてはいないが、このようにするとうまくいく」というような暗黙の業務の進め方があったり、「この業務のことはこの人に聞けばうまくいく」というような「生き字引」のような人が、企業にいるといった文化があります。
より特徴的な例を出すとすれば、職人文化もそれにあたります。
職人が生み出す「一点もの」の製品は、データや数字に表すことが困難で、熟練職人の勘だよりな部分が製品製造の場面でしばしば見られます。
もちろん、こうした「長年の勘」や、「経験から得られる感覚」を悪しき伝統として拒絶するのはやや極端です。
長年同じ業務に携わってきた経験がある人には、やはり一定程度の「経験から得られる生きた知識」というものがあり、それは尊ばれるべきものです。
問題はむしろ、そうした知識や経験の継承が、難しいことです。
これらの継承が難しい「暗黙知」がどのように継承されてきたかといえば、かつての日本企業の文化としては「見て盗め」が常套句でした。
新人や若手は先輩社員・職員の仕事の進め方をとにかく観察し、先輩社員から言語による伝達ではなく、体感によって業務の勘をつかませるということが行われており、それこそが経験を積むという認識が一般的だったのです。
日本企業でも重視されるようになってきた「形式知」
さて、このように日本企業や職人の世界では、「暗黙知」に該当する、経験から得られた知識は経験によってしか得られない、という認識が一般的であったことから、言語化して部下や新人、若手に業務知識を継承・伝達することはあまり行われてきませんでした。
しかし、近年では「マニュアル化」「数値化」をすることで、従来「暗黙知」の領分であったものが、実は言語化して伝えることができるものであった、ということが判明するケースが多くあります。
それと同時に、なんでも「見て盗め」という態度でいることは、業務知識の共有という重要な継承行為に対する怠慢だという風潮すら生まれてきました。
このように、言語化・マニュアル化・数値化という、「目に見えるもの」に業務知識を落とし込み、それを共有することが出来る状態になっている知識のことを「形式知」といいます。
かつては、言語化ができない、言葉では伝えられないとされてきたものが、データや数値で人に共有することができるようになり、日本企業、特に暗黙知を重視してきた職人界隈においても、現代では「形式知」が重要視されるようになってきています。
暗黙知を形式知化した具体例

そうは言っても、やはり伝統の技や経験を言語化するのはやはり困難なのではないか?と考える方も多いでしょう。
もちろん、すべての知識が、形式知化できるわけではありません。
暗黙知とはその人の「業務知識」だけにフォーカスするものではなく、その人が歩んできた人生や、それによって得られた経験にも裏打ちされているからです。
しかしながら、データや数値といったものの「不可侵領域」とされてきた伝統の知識や技にも、データや数値が深く関わっていたことがわかり、それを形式知化した、つまり数値化した事例があります。
日本酒の発酵・醸造を行う日本の伝統的な職人技である「杜氏」についても、かつては発酵の度合いやタイミングなどは暗黙知の扱いを受けており、熟練の職人にしかわからないもの、という認識が一般的でした。
しかしながら、ある杜氏が技術伝承のためにもろみの発酵度合いや中心温度をライブカメラで記録して徹底的にデータ化を試み、最適な発酵具合を数値とデータで見極められるようになったという事例があります。
もちろん、従来の杜氏はこのような方法で発酵度合いや温度を管理していたのではなく、あくまで「体感」でそれらを計測していました。
ですが、熟練の杜氏が体感によって見極めていたタイミングは、数値によって明らかにすることができたのです。
他にも、囲碁のAIに形式知を見出す人もいます。
囲碁は従来、棋士が素人には判別困難な展開を読んで、後々のことを見通して手を指しているから勝てるのだ、という風潮がありました。
しかし、囲碁AIの思考パターンから、局面ごとの最適な手を導き出すことができるようになり、その局面での最適手がいかにして判断されるか、ということを教本に書くことができる、つまり形式知化することができたのです。
このように、従来「暗黙知である」とされてきたものを、形式知化することができた事例は数多く存在します。
暗黙知と形式知を管理するSECIモデル
企業での仕事においても、長い期間勤めることによって得られた経験や勘が、暗黙知化してしまっているケースがあります。
これを形式知化して共有することができれば、組織やチームにとって大きなメリットとなるでしょう。
こうした知識の管理の手法として、「SECIモデル」と呼ばれる方法があります。
このSECIモデルとは、知識の段階を「共同化」「表出化」「結合化」「内面化」という4つのフェーズに分けて、知識の浸透と共有をはかるというものです。
「共同化」は、グループで暗黙知を共同化・新たな暗黙知の創造をします。
これは、グループで新たな業務にあたらせることなどで、各自にノウハウを得させるフェーズと考えるとわかりやすいでしょう。
次に「表出化」では、グループの構成員それぞれが持っている暗黙知を話したり、書いたりすることで表面に発表させます。
そして「結合化」では、「表出化」によって出された暗黙知を結合し、新たな知識を創造します。
これが「形式知」となります。
そして「内面化」では「結合化」や「表出化」された知識・経験を再度グループ内で、共有し、自分の中に落とし込むという作業をします。
こうすることで、各構成員の持っている暗黙知が一度表に出され、それがマージされてそれぞれの知識として定着させられるという「共有」が可能となるのです。
まとめ

日本企業においては、「暗黙知」が尊いものとされすぎて、それを形式知化する、つまり共有して継承するという点が軽視されてきたという歴史があります。
せっかく事業の担い手が現れても、知識や経験の共有を怠り暗黙知化してしまうことで、担い手の不足を招いたり、事業の継承にトラブルが生じるケースもあります。
もちろん暗黙知は共有が難しいものであるという前提がありますが、円滑な業務進行のためには、その困難に対して少なくとも「共有する努力」「形式知化する努力」が行われるべきであるといえるでしょう。