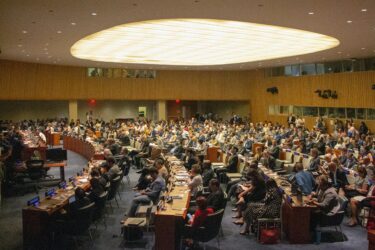SDGsの導入には「バックキャスティング」の思考が必要と言われておりますが、「そもそもバックキャスティングってなに?」という人も多いことでしょう。
企業経営にSDGsを導入するにあたって、バックキャスティングを理解することが近道となります。
この記事でSDGsとバックキャスティングを理解して、SDGs導入の参考にしてください。
真逆の手法であるフォアキャスティングとは?

まずは対照的な思考法であるフォアキャスティング(Fore casting)について触れておきます。
多くの企業が目標設定などで使用する手法です。Fore(前)から未来に向かって積み上げていく方法で、過去→現在→未来という時系列で目標や計画をたてます。
過去の売上実績から来年度の売上目標を立てるなどが一例で、実現可能性がある程度計りやすく、適度なレベルの目標設定となります。どの企業も採用している、ごく一般的な目標設定の手法です。
バックキャスティングについて解説
先述のフォアキャスティングに対して、「未来のあるべき姿」から逆算して現在の対策を考える思考法をバックキャスティング(Back casting)といいます。
短期的な目標ではなく、10年〜20年といった長期的な目標設定や、現時点では難易度が高い目標を設定する際に使われる手法となります。
フォアキャスティングはどうしても過去や現在を起点に目標設定をするため、現実的な目標になりがちです。
バックキャスティングの手法を使えば、長期的な視点となるため、大きなイノベーションなど難易度の高い目標を設定しやすくなります。
SDGsはバックキャスティング思考法?
SDGs(持続可能な開発目標)は、2030年までに達成すべき国際目標として掲げられました。
地球規模の持続可能な目標として、経済、社会、環境のすべての課題に対応した17の大きなゴールと169の具体的なターゲットが設定されています。
あらゆる面での課題において、「誰一人取り残さない」世界を目標としています。
SDGsは2030年までに達成すべき持続可能な開発目標という、バックキャスティングの手法で設定されています。
17の目標と169のターゲットが達成すべきゴールとして掲げられており、まさにバックキャスティングの考え方が当てはまります。
バックキャスティングによるSDGs導入ステップを解説
SDGsもバックキャスティング思考の考え方で作られているため、企業がSDGsを導入する際もバックキャスティング思考が必要となります。
そこでバックキャスティングによるSDGs導入のステップを以下の5つで解説します。
ステップ1:SDGsを知る
バックキャスティングでいきなり目標を設定する前に、まずはSDGsを正しく理解しましょう。
SDGsは17の大きな目標と169のターゲットで構成されておりますが、「5つのP」からみていくと全体像をつかむことができます。
全体像を把握したら、具体的なターゲットをみていきましょう。自社で貢献できそうなものをいくつかピックアップしておくと、目標設定までスムーズに進むことができます。
ステップ2:達成すべき目標を設定する
いよいよバックキャスティングの出番です。自社の未来における「あるべき姿」を描きましょう。
SDGsの17の目標や169のターゲットのどれに沿ったものかを意識して目標設定します。
掲げられた目標に沿ったものであれば、SDGsへの貢献度が高まります。課題が複数ある場合は優先度の高い課題にのぞみましょう。
それが自社にとっての「あるべき姿」となります。優先度の低い課題へ取り組んだ場合、SDGsへの貢献度が低く、組織の意欲も低下する可能性があります。
ステップ3:目標達成に向けた課題の洗い出し
たとえば「2030年までに女性管理職の比率を50%とする」を設定した目標とします。
そのためには女性が管理職として登用されやすい環境整備が必要です。
たとえば、育児休業制度の拡充や子育てと両立しやすい勤務スタイルの導入など、現時点で考えられる課題を挙げていきましょう。
あらゆる面で目標設定に向けた課題の洗い出しを行うことが重要です。
ステップ4:目標達成に向けたKPIの設定
ステップ3で挙げた課題の解決のため、具体的なKPIを設定しましょう。
さきほどの例から、以下のようなKPIを設定します。
「2023年までに子育て特別休暇の取得率100%を達成する」
「2025年までに育児休業制度を確立し、女性の産後復帰率を100%とする」
「あるべき姿」である「2030年までに女性管理職の比率を50%とする」を達成するために具体的なKPIを設定することが重要となります。
ステップ5:定期的に見直し、ステップ3と4でPDCAをまわす
「あるべき姿」に向かうなかでステップ3で定めた課題が変わったり、ステップ4のKPIを変える必要があるかもしれません。
外的要因によってKPIを大きく変える必要も出てくることでしょう。定期的にKPI状況を見直しながら、「あるべき姿」に必要な新たな課題を模索していく必要があります。
ステップ3と4でPDCAをまわしながら、「あるべき姿」を目指していきましょう。
バックキャスティング導入におけるポイント
・「あるべき姿」を忘れない
バックキャスティングを導入する中で、未来から逆算して現在を考えますが、現時点での正解にこだわらないことが大事です。
現時点では進むべき正解が見つからないかもしれません。正解が見つからないことで、達成不可能と判断してしまっては本末転倒となります。
正解が見つからなくても「あるべき姿」を忘れずに、まわり道をしながらでも到達することが大切です。
あくまで取り組むことが可能な課題をPDCAをまわしながら解決していくことで、「あるべき姿」を目指しましょう。
・ステークホルダーへの説明
従業員などステークホルダーへのバックキャスティング思考の説明は重要となります。
SDGsへの理解度も組織全体で高める必要があります。
SDGsはバックキャスティング思考をもとに掲げられていますが、説明不足のまま、バックキャスティング思考法を取り入れるのは難しいでしょう。
これまでフォアキャスティング思考で目標を設定することが多い企業はなおさらです。
現在を起点に考えてしまうと、「あるべき姿」の難易度によっては、「目標達成は現実的ではない」という反発につながる可能性があります。
長期的で難易度の高い目標となる「あるべき姿」を目指すために、ステークホルダーへの説明が大きなカギとなります。
・強いリーダーシップの発揮
10年スパンの高い目標を掲げて、従業員とともに「あるべき姿」を達成するためには、経営陣の強いリーダーシップが必要です。
経営陣側と従業員側とで認識に差があると、目標達成が遠のいてしまいます。
組織全体のコミュニケーションを強化し、強いリーダーシップで「あるべき姿」を達成しましょう。
おわりに

バックキャスティングについて、SDGsとの関係、導入ステップやポイントを解説しました。
SDGsのような長期的でチャレンジングな目標は、バックキャスティング思考が重要となります。
しかしながら従来のフォアキャスティングと上手く併用することも大切です。
SDGsへの貢献はもちろん、持続可能な企業を目指すために「あるべき姿」の目標設定に取り組んでいきましょう。